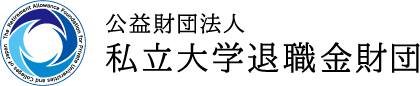手仕事の美を伝える染色と民藝の空間(東北福祉大学)
学食・博物館特集Date: 2025.08.20
大学ミュージアム図鑑 [第5回]
東北福祉大学 芹沢銈介美術工芸館(栴檀学園)

※2025年8月発行BILANC vol.37に掲載
構成:八色祐次
撮影:森本真哉
編集:プレジデント社
手仕事の美を伝える染色と民藝の空間
~人間国宝の作品と世界の工芸品が集う場所
型絵染の技法で人間国宝に認定された、日本を代表する染色家・芹沢銈介(せりざわけいすけ)。
彼の作品約300点と関連資料2700点と、工芸品の収集家としても知られた彼の世界各地の工芸コレクション約1500点、作品に用いた型紙約1万点を所蔵しているのが、東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館です。
型絵染とは、型紙を使って布を染める技法の一つ。生活の道具がもつ美を提唱する「民藝運動」に関わっていた芹沢は、着物や帯、のれんの他、屏風、扇子、装幀など、暮らしに密着したさまざまな作品で知られています。

鯛の模様のダイナミックな配置が目を引く、芹沢の代表作の一つ『鯛泳ぐ文着物』。
「一般的に“型絵染”は、図案を描く絵師、型を彫る彫師、布を染める染師といった分業制でつくられますが、芹沢は図案から型紙彫り、染めまでを一貫して手掛けました。そのため、作品からは芹沢のオリジナリティを強く感じることができます」(学芸員・堀咲さん)
独創的な文様と、晴れやかでありつつ落ち着きも感じられる配色、余白まで考え尽くされた模様の配置など、新しさと懐かしさが同居した作品の数々を楽しむことができる空間です。

美術館の吹き抜けになったロビーの天井にあるステンドグラス。
芹沢最晩年のステンドグラス図案になった炎と蓮、縄文様、山並文様を使いデザインされている。


1946年からおよそ40年間つくられた『型染カレンダー』。和紙に 型紙を用いて顔料などで模様を染める技法は芹沢が創案したもの。
カレンダーは、アメリカ占領下に米軍将校の 妻らからの強い要望で考案されたといわれる。
ほかにも型絵染によるタイトル文字や装画、和紙の質感を生かしたあしらいなど、装幀や日常品も多く手掛けた。
芹沢作品を所蔵する美術館は、彼の存命中に静岡に建てられました。しかし、芹沢が晩年「仙台にも陳列館を」と言い残したことを受け、1989年、東北福祉大学に芹沢銈介美術工芸館を開設。
民藝の精神を伝え、生きた学びに昇華するこの場は、「行学一如」(学問研究と実践実行は全く一体であること)の理念を掲げる同大学らしいといえるでしょう。
「1930年代、若き日の芹沢は東北の窯場を訪ねて焼き物を主題に作品を制作したり、青森で小絵馬を収集したりしていました。東北の風土や文化に、ひときわ愛着を抱いていたのです」

芹沢の暖簾は、ワンポイントの模様とその絶妙な配置が特徴。
日常の中にある美しさをみつめ、感性を育てる
芹沢銈介美術工芸館は一般開放されているため、オープン以来、全国から多くの人が来館し、人間国宝の手による作品や彼のコレクションに親しんでいます。また、第一級の作品に触れることは、学生の感性教育にも役立っていると堀さんは指摘します。
「目の前のものを丁寧に観察し、わずかな変化を感じ取る感性は、福祉に携わる人にとって欠かせないものです。相手が人か美術品かの違いはあっても、本物の美術品がもつ美しさや質感に触れることで、物事の微細な変化に気付く感性が養われるのだと思います。一部の展示室には、学生が作品を眺めながらゆっくり過ごせるよう、机と椅子も置いており、読書などをする学生の姿もみられます。作品の美に触れ、この空間に身を置いた経験が、少し先の未来、学生の心の中で何かを咲かせてくれることを願っています」

芹沢によるガラス絵。ガラスの裏面から絵具を重ねて描いていくため、鮮やかな色彩も相まって奥行が感じられる。
前回までの博物館ご紹介の記事はこちら
○ 楽器ミュージアム(武蔵野音楽大学)
○ 「食と農」の博物館(東京農業大学)
○ 恐竜学博物館(岡山理科大学)
○ 大阪青山歴史文学博物館(大阪青山大学)