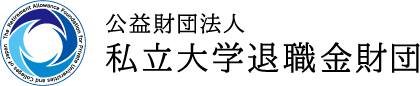東北芸術工科大学 文芸ラジオ
未来を拓く学校人Date: 2025.08.20
“つくる”を超えて“届ける”へ。
文芸誌で挑む、社会との対話

文芸学科の教室にて。毎号の企画会議では、学生と教員が一緒になって、編集部員としてアイデアや意見を交わす。
※2025年8月発行BILANC vol.37に掲載。インタビュイーの役職等は取材時のものです。
構成:八色祐次
撮影:森本真哉
編集:プレジデント社
~自覚と責任を育てる、「実践の場」を目指して
東北芸術工科大学は、山形県と山形 市の強い要望を受け、1991年に創立されました。
「人類の良心に根ざした芸術と工学の力で、社会に貢献する人材を育成する」という教育理念のもと、多彩な人材を輩出。第66回小学館漫画賞・少年向け部門受賞『チェンソーマン』の作者・藤本タツキ氏をはじめ、写真家、映画監督、小説家など、各界で活躍するクリエイターたちが巣立っています。
同大学の文芸学科は、小説などの創作に加え、編集や出版など幅広い視点から「言葉の表現」を学び、アートやデザインと横断的に関わりながら、独自の創作活動を追求できる点が特徴です。文芸学科の教授・玉井建也さんが講師として着任した翌年、学生たちとともに創刊したのが、文芸誌『文芸ラジオ』です。
「文芸学科の学生たちに、プロと一緒に、プロの現場で、編集者としての実践の場をつくりたかったのです」。玉井さんは、刊行の背景についてそう語ります。
小説家や漫画家を目指す学生たちは、賞レースに投稿することでアウトプットの機会を得て、経験値を高めることができます。しかし、編集志望の学生には、そのような場がありませんでした。
「『文芸ラジオ』を立ち上げる前は、学生たちが集まって同人誌をつくっていました。でも、同人誌の世界は馴れ合いになって内輪で完結してしまいがち。本当に必要な経験とは、自分たちが手がけた雑誌が書店に並び、不特定多数の読者の目に触れ、手に取ってもらうまでやり切ることだと考えたのです」
 |
東北芸術工科大学 芸術学部 文芸学科 教授 玉井 建也さん 誌面制作を通じて 学生には、既成の枠を 飛び越えてほしい |
玉井さんがこう語るように、『文芸ラジオ』は出版コードを取得し、全国の書店に流通しています。学生たちは、自ら手がけた雑誌が書店の棚に並ぶ喜びを通じて、「読者に届くものをつくる」という自覚と責任を実感できるのです。
その意識をより強く持ってもらうため、企画立案から取材対象者の選定、アポイント、取材、執筆、校正まで、編集作業の多くを学生が担当。アポイントを取る大変さ、引き受けてもらえることの貴重さ、締め切りの重要性など、学生のうちはなかなか触れることのない業務に関わることができます。なかでも貴重なのが、校正・校閲作業。作家が書いた原稿に修正を加えるという重要な工程に携わる機会は、そう多くはありません。教員は必要最低限のサポートにとどめ、学生たちが主体的に学び、社会人として成長できる場として運営されています。
「編集者やライターとして活躍する卒業生からは、『本来は社会に出て初めて直面する業務を、学生時代に一通り体験したことが、現場で武器になっている』との声が寄せられています」(玉井さん)
また、学生の作業が思い通りに進まないことも、貴重な成長の機会と捉えています。そうした場合には、教員が適切にサポートし、完成へと導いています。
~学生同士で問いを重ね、企画を社会に届ける
『文芸ラジオ』の発行は年1回。1年次は授業の一環として、2年次以降は有志の学生が中心となって制作されています。制作のスタートは毎年5月頃。学生たちが関心のあるテーマや企画を自由に出し合うところから始まります。
「学生同士でアイデアを出し合う中、最初に出てきたテーマが“豆腐メンタル”という言葉です。心が豆腐のように柔らかく、ちょっとしたことですぐに傷ついてしまう。最近の若い世代には、そんな精神的な脆さがあるのではないか、という気付きが発想の出発点でした」
こう語るのは、最新11号で編集長を務めた小笠原星さん(3年生)です。ただ、“豆腐メンタル”は以前の号に似たようなテーマを取り上げたことがあったため、教授からアドバイスをもらい、ここを起点に考えをさらに深めていきました。
「確かに、精神的に弱いと感じられる若者もいるかもしれません。でも、やるべきこと、やりたいことに一心に取り組んでいる若者も多い。つまり、内に秘める熱いものは、昔と変わっていないのかもしれないと考えました。昔は、やる気を全面に出す熱血主人公がよく描かれていましたが、今の若者はその熱さを表に出さないだけ。むしろ内側では、同じかそれ以上に強い思いを持っているのではないか。そんな仮説や意見交換から、企画が膨らんでいきました」(小笠原さん)
 |
東北芸術工科大学 芸術学部 文芸学科 3年 小笠原 星さん アイデアの断片に “なぜ”と問いかけながら 自分たちらしい企画に! |
実際、最近の物語作品でも、心の中で静かに闘志を燃やしながら、それを周囲に悟らせないキャラクターやストーリーは人気を集めているといいます。『文芸ラジオ』ではこの傾向から、企画テーマを“ステルス本気論”と名付けました。
企画テーマが定まった後は、詳細を詰めていきます。
「若者たちの実態を捉えるためには、まずはいちばん身近な学生たちの声を聴くことが欠かせません。そこで、編集一方で、小笠原さん率いるチームは、創作物に登場するキャラクターを通して“ステルス本気”の姿を掘り下げようと試みました。心理学の「ジョハリの窓」という自己理解モデルを応用し、タイプごとに分類・分析することに挑戦したのです。分析対象となる創作物の選定にあたっても、明確な基準を設けました。
「チームメンバーそれぞれが20~50冊を手に取りましたが、やみくもに読み漁るのではなく、直近5年間に発表された作品、かつアニメ化されるなど一定の認知度があるものに絞りました」と小笠原さん。話題性のある作品を通して、現代の若者が共感しやすいキャラクター像を抽出しようとしたのです。
このように、若者のリアルな声と、創作物に描かれる人物像という2つの視点から、現代の若者が心の奥底に秘める熱量を解き明かそうとしたのが、今回の取り組みでした。
話し合いを経て、今号の表紙を飾るのは、『スーパースターを唄って。』(ビッグコミックス)の作者・薄場圭氏に決定。「絶望的な環境で生きる少年が、あるきっかけから、ラップで心の内を吐露するようになり、過酷な世界から這い上がっていく―その姿が、“ステルス本気”に重なると感じたのです」(小笠原さん)

テーマや表紙デザインは号によってさまざま。学生がつくるからこその多様性を大切にしている。
高野さんのチームは、アンケート調査で得られたデータをより深く掘り下げるため、専門家に意見を求めることに。依頼先として選んだのは、若者研究の第一人者として知られる、マーケティングアナリストの原田曜平さんでした。
「若者研究の専門家が、アンケート結果をどう分析するのか知りたかったのです。原田さんはメディアでのご活躍も多く、幅広く知られています。読者の皆さんにも説得力があるのではないかと考え、依頼することにしました」(高野さん)
学生らしいアイデアの断片に対して、教員が適切にフォローして学生のアイデアを社会とつなぎ合わせる。企画の方向性を磨いた上で、どうすれば読者に伝わるのか、楽しんでもらえるのかを考え抜き、最適な表現方法を探し続ける—。単なる授業や課題制作を超え、社会とつながる場での試行錯誤が、学生にとっての貴重な実践教育となっているのです。
 |
東北芸術工科大学 芸術学部 文芸学科 3年 高野 功雅さん プロフェッショナルの言葉を 直接聞くからこそ より強く、心に響く |
~プロ意識に触れることが新たな気付きにつながる
雑誌制作にあたり、社会で活躍するクリエイターへのインタビューも、学生に新たな気付きをもたらしています。
「数々の作品を世に送り出している人気作家さんのお話が印象的でした。作品は、細かいディテールももちろん大切ですが、それ以上に、物語の大筋や構成こそが重要だと話されていたのです。あのインタビューをきっかけに、企画の立て方や、創作への向き合い方が、大きく変わったと感じています」(高野さん)
また、インタビューの内容だけでなく、原稿確認のやり取りからも学びを得たと語るのは小笠原さんです。
「あるアーティストの方にインタビュー記事の内容確認をお願いした際、記事を通してご自身がどのように伝わるかにも心を配っていらっしゃることを感じました。表現の世界で活躍する方々は、作品だけでなく、自分自身の見せ方や伝え方までしっかりとプロデュースしているんだと、改めて気付かされました」
自分たちで考えて選んだ作家やアーティストだからこそ、その言葉から得られるものも多いはずです。第一線で活躍するプロの言葉に触れることは、学生に多くの気づきを与えてくれるでしょう。
「従来の文芸誌は、純文学なら純文学、ミステリーならミステリーと、ジャンルごとに構成されるのが一般的です。一方、『文芸ラジオ』が目指しているのは、一つの色に染まるのではなく、さまざまなジャンルやアーティスト、タレントが登場し、まるでラジオ番組のように多様で自由な誌面づくりです。その年々の学生の色をさまざまな形で出し、また、学生ならではの柔軟な発想で、新しい表現を生み出してほしい。そして、『文芸ラジオ』の制作を通じて、既成の枠を一歩超えた、新たな文芸のかたちに挑戦してほしい—そう願っています」(玉井さん)
形式に縛られず、自分たちの感性で新しい文芸の世界を切り拓く『文芸ラジオ』。こうした実践的な学びの場は、創造力や主体性を育む貴重な機会となり、社会との接点を通じて、多様な視点や課題意識を育てる場となっています。
※ 私立大学退職金財団では、教職員の皆様にスポットをあてた「未来を拓く学校人」の情報を募集しています。掲載をご希望の維持会員は、当財団までご連絡ください。