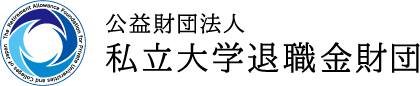“人間力”で未来を拓く(上野正雄氏)
私大等の今を聞くDate: 2025.08.20
私立大学は教育・研究機関として次代を担う人材の育成という、重要な役割を担っていますが、その経営は大きな課題となっているのが現状です。今後どのような展望が考えられるのか、明治大学学長の上野正雄先生にお話を伺いました。
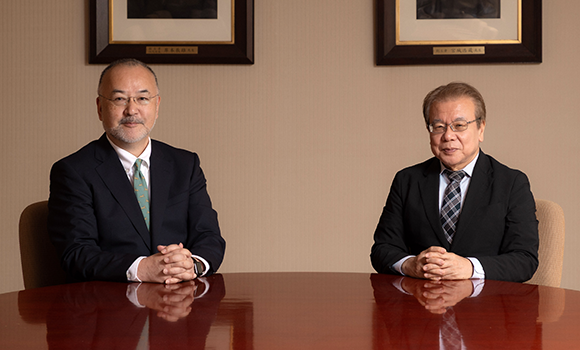
左から明治大学 上野正雄学長、当財団 守田芳秋常務理事
※2025年8月発行BILANC vol.36に掲載
構成:八色祐次
撮影:小田駿一
編集:プレジデント社
~明治大学のあるべき姿
守田 私立大学は教育・研究機関として次代を担う人材の育成という、重要な役割を担っています。しかし、募集を停止する大学・短期大学が増加するなど、その経営は大きな課題となっているのが現状です。そこを踏まえつつ、今後どのような展望が考えられるのか、私学は何をなすべきなのか、お考えを教えていただけないでしょうか。
上野正雄先生(以下「上野」) 18歳人口の減少など課題が山積している現在、各大学が孤立していては存続しえませんし、社会の負託に応えられないと考えています。大切なのは、現在の、そして将来の学生の皆さんが大学に期待しているニーズに応えることです。そのためには、総合大学や単科大学、都市部の大学や地方の大学、それに多種多様な研究分野など、幅広い選択肢を学生に提供する必要があると考えます。そのうえで本学には何ができるのか、「明治大学のあるべき姿」を考え、追求していくことが重要だと思っています。
守田 明治大学のあるべき姿とは、どのようなものでしょうか。
上野 明治大学には10学部16研究科があります。この教育研究の層の厚さを、一人ひとりの学生に還元していきたいと考えています。従来は、学部の中で学びは完結しました。でも、それではもったいないと思うのです。せっかく幅広い学部、研究科があるのですから、学生が学部等の垣根を超えてもっと自由に学べるよう環境を整えていくべきではないだろうか、と。そうすることで、一つの分野だけを学んで満足するのではなく、大学でいろいろな学問を学びたい、いろいろな人と関わってみたいといったことを望む学生のニーズに応えられると思うのです
守田 具体的には、どのような施策を行っているのでしょうか。
上野 例えば「全学共通総合講座」というものがあります。これは、学部や文理の枠を超えた学際的講義で、幅広い学問的視野や問題発見能力などを培うため、学生にとって有益となるテーマのもと多様な講座を設定しています。
ほかに、所属する学部以外の分野を学ぶことができる「副専攻プログラム」も導入します。
~多様な選択肢で教育の質向上を
守田 文理横断や融合教育などは、中央教育審議会で取りまとめられた「我が国の『知の総和』向上の未来像」内でも、重視すべき観点として触れられています。教育の質を上げていくためには、大学として何をすべきだと考えますか。
上野 全学共通総合講座や副専攻プログラムのように、教育の機会や選択肢を増やしていくことは欠かせません。なぜなら、複雑化している現代社会では、一つの見方で課題や問題を見極めることが難しくなっているからです。例えば、問題提起するとき、法学部の学生だと事象を法律の側面からだけ見て、何が問題なのかを考えがちです。しかし、社会学的な視点で見た場合、そこは争点にならないかもしれません。また別の学問から見ると、むしろ歓迎すべきことという可能性もあり得ます。
これからの社会において必要とされる人材の素養の一つに、何が問題なのかを見出し問題提起することがありますが、その見極めには複数の視点から事象を観察することが不可欠でしょう。だからこそ、大学教育において、複眼的な思考力を培うことが大切だと思うのです。世の中のさまざまな事象の中で何が問題なのかを見極める力が弱いことが、ここ数十年の日本の停滞につながっているのではないかと感じているくらいです。
守田 学生の教育支援施策には、他にどのようなものがあるのでしょうか。
上野 2025年4月にアントレプレナーシップ(起業家精神)教育と実際の起業支援業務を行う組織として「起業・スタートアップ支援室」を開設しました。これは、スタートアップの入門教育を行う全学共通総合講座の運営や学生の起業活動支援など学内のスタートアップ関連活動のハブとなって、人的・教育資源を集約する目的を担う組織です。
本学の校友(卒業生)には、社会で活躍している方がたくさんいます。さまざまな企業、多様な部署において成果を出している先輩方や、士業など専門性の高いスキルを活かして多くの人たちをサポートしている先輩方など業種業界、立場などもバラエティに富んでいます。そのような校友と、支援を必要としている学生起業家、これから起業を考えている学生とをマッチングして大学にいながら実践的なノウハウに触れ、経験を積める環境を提供していきたいと考えています。
~研究に集中できる環境づくり
上野 教育の質を上げるということを考えるときに大切なのが研究です。先生方が研究に打ち込むことで培った知見や成果を、学生に還元してもらわなければなりません。明治大学では研究支援体制の充実にも力を注いでいます。
守田 具体的にはどのような取り組みを実施しているのでしょうか。
上野 明治大学の建学の精神は「権利自由、独立自治」です。そこからしても先生方の研究内容にまで踏み込むことはありません。その前提において何ができるのかを考え、バイアウト制度(研究以外の業務の代行に係る経費を競争的研究費の直接経費から支出可能にする仕組み)やPI(研究代表者)人件費支出制度を導入しています。研究者が研究に専念するための制度としては、大学リサーチアドミニストレータ(URA)の導入に向けて手続きを進めているところでもあります。
守田 明治大学では、研究者が学内業務から解放され、研究に集中することができる「サバティカル制度」も取り入れていますよね。
上野 はい。国際的な研究ネットワークの形成や拡充が大学の研究力向上にとって、非常に重要だと考えるからです。その一環として、海外の優秀な研究者の招へいや国際学会の開催などを今後さらに積極的に推進していく予定です。加えて、次代を担う若手研究者の国内外での国際的研究交流の機会創出のための制度を抜本的に改革していこうとしているところです。
守田 2025年度の学長方針の表題に「人間力で未来を拓く」とありますが、教育と研究の両輪を深化させていくことによって、どのような人材を育成していこうと考えているのでしょうか。
上野 自分自身だけでなく、他者も最大限に尊重できる人材でなければ、権利自由、独立自治を推し進めることはできないと考えています。そのため、自分自身も他者も大事にできる人間を育成していきたいです。ただ、これは教室における教育だけで実現できることではありません。学生同士や学生と教職員、教職員同士の関係性から生まれるものなど、さまざまな人との関わり合いの中で身につくものです。このような機会を創るという意味でも、明治大学で実践している過半数の授業クラスが30人未満という全学的な少人数教育も役に立っていると考えていますし、学部や研究科の枠を超えた交流も人間力育成にいい影響をもたらすと信じています。
守田 貴学の取り組みに期待しています。本日はありがとうございました。
 |
お話を伺った方 |