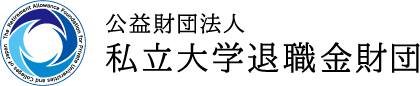"社会実装"で次代の教育へ(丸山 悟氏)
私大等の今を聞くDate: 2025.03.21
少子化や地方格差、大学改革など、私立大学等を取り巻く状況は変化し続けています。そのようななか、各学校法人はいかにして存在感を発揮すべきなのでしょうか、日本福祉大学理事長の丸山 悟先生にお話を伺いました。

日本福祉大学 丸山 悟理事長
※2025年3月発行BILANC vol.36に掲載
構成:布施 恵
撮影:川島英嗣
編集:プレジデント社
~18歳人口の減少を迎えて
超少子高齢化社会による若年労働力不足の状況下では、コロナ禍で定着したDXの力を最大限大学も発揮していく必要があり、また教育の多様化が求められます。オンラインと対面を組み合わせたブレンデッド教育は有効ですが、教員の負担が大きくなります。また、留学生教育でも、わかりやすく教材にキャプションをつけることは有効ですが、これもまた大きな負担です。これらをサポートする運営側の工夫が求められるでしょう。
さて、日本人の18歳人口が減少局面を迎える中、それ以外の入学者をいかに獲得するかが、今後重要になります。まずその対象になるのが社会人、その次が留学生です。そして、大学の機能として、入学者はもちろんのこと、小学生や中学生も含めた社会体験が乏しい生徒に向けては、実際にモノや人に触れるといった授業に対しての実践(補強)、つまり生涯教育の提供が期待されています。言うなれば単なる論理ではなく、“実践知”となるような指導が必要となるでしょう。
規模の大きな私立大学は小中高大一貫の連続したシステムをすでに持っているため、年少者を対象にした授業が増えれば、よりその構造が強みとして発揮できる時代になるのではないでしょうか。本学においては大学以下の教育機関は高校のみとなるため、対象を近隣の公立小中学校に広げて実践的な教育の提供を行う必要性があると考えています。
~“Well-being”を追求する
本学は1953(昭和28)年に中部社会事業短期大学としてスタートし、今年の4月に半田キャンパスに開設される工学部を含めると、現在では9学部11学科を備える「ふくしの総合大学」へと成長しました。
私たちが、福祉をあえてひらがなの「ふくし」で表現しているのには理由があります。まずは、社会福祉の単科大学ではなく、幅広い分野を学べる総合大学であるという価値を示すためです。そして、「“ふ”つうの“く”らしの“し”あわせ」の頭文字を表すため。
この「ふつうのくらしのしあわせ」という言葉は、憲法第25条の「健康で文化的な最低限度の生活」と憲法第13条の幸福追求権から生まれたもの。働きがいのある仕事(Decent work)を追求し、人々の幸せに教育を通じて貢献したい、という本学の目指す姿を示しています。
そして、学園創立70周年を迎えた2023(令和5)年、事業推進のテーマとして「Wellbeingfor All」を宣言しました。このWell-beingという言葉は、世界保健機関(WHO)の憲章に出てくるもので、身体、経済、文化、社会的にも良好な状態のことを表しています。個人の身心だけではなく、社会的にも満たされ、かつ世界全体(地球社会)にとっても“良い状態”を追求していきたい―。この宣言に沿って、今後はキャンパス内での社会実装と一体でのコミュニティづくりに重きを置いていきたいと考えています。
社会実装とは、知識や研究の成果を課題解決に活用すること。今後、教育・研究の両面で重要なテーマになると考えています。具体的なカリキュラムでいうと、フィールドワークや実習、インターンシップなど。それから社会課題を直接検討する演習やゼミに大きく重点を置き、教育・研究の両面においての社会実装というインパクトのある目標を掲げています。
~キャンパスは学術都市
この学園創立70周年という大きな節目にあたり、本学は大きく3つの骨格事業を策定しました。
まずは、「Well-being for All」を目指した社会実装型キャンパス創造と環境整備。その実現に向け、2024年10月に愛知県名古屋市で開業した国内最大のスタートアップ支援施設「STATION Ai」に、本学も参画しています。同施設は国内外の新興企業を受け入れるほか、地元を中心とした有力企業、金融機関や大学などの研究機関約200社が参入するもの。各社と協業、支援し合うことで、社会実装に向けた新しい技術や事業の創出を目指しています。
2つ目は、次世代育成のための教育・研究の推進です。自治体と協力しながら高校以下の子どもたちに向けた教育の実践の場を提供していきます。その1つが、部活動の地域移行を目指したスポーツクラブの立ち上げ。少子化が深刻化する中、市町と協働して子どもたちがより成長できる環境をつくっていきたいと考えています。
3つ目がリカレント教育の充実。2024年に大学の付属機関の1つとして社会人を対象にした「FUKUSHI ACADEMY ![]() 」を開設しました。このアカデミーでは、ふくし現場の課題解決に向けて、現職者向けの学び直しプログラムなどを開発・提供。そして、実践家と研究者の協働研究を推進しています。
」を開設しました。このアカデミーでは、ふくし現場の課題解決に向けて、現職者向けの学び直しプログラムなどを開発・提供。そして、実践家と研究者の協働研究を推進しています。
また、2027年4月には東海キャンパスの西側を拡張し、現在、美浜キャンパスにある社会福祉学部を移転予定です。東海キャンパスの新コンセプトは“学術研究の都市”。大学に在籍している人以外もキャンパス内を日常的に出入りし、コモンズという互いに探求・議論しコラボレーションできるような場をつくる。そして、学生自ら問題への答えを見つけていく、そんな新キャンパスを目指しています。
~「余剰」がなぜ必要か
コロナで学んだことは、「レジリエンス(回復力)」と「ロバストネス(変化を受けにくく機能を維持する仕組み)」の大切さ。この2つに共通することは、「余剰」をつくっておかなければならないということです。
冗長性がないところでは、コロナのように何か想像を超える出来事が起こったときに、対応することができません。18歳人口の減少が進む中で、私立大学はこの余剰を大きくする方法を真剣に考える必要があるでしょう。
また、コロナ禍は人と人の相互依存関係を明らかにしました。誰しもが被害者にも加害者にもなる状況の中、互いに支え合いや配慮を行うことが求められたと思います。この相互依存関係で立場を形成していくことは、まさにケアの思想ともいえるでしょう。そういう意味で大学においてもケアリングコミュニティのように、お互いを力強く支え合う“相互依存関係”の仕組みを構築し、積極的に「余剰」をつくることが重要なのです。そのためには、自分にはないものを補強する動きが必要になるでしょう。最近は、「地域おこし」に取り組む企業や団体が増えています。総務省の事業である、移住して地域価値の向上に取り組む「地域おこし協力隊」のメンバーは5000人を超えました。
規模の縮小が避けられない時代だからこそ、大学は地域と密接に連携し、行政や企業や労働団体等と“連合”を組みながら、まち全体で教育に取り組むことが求められています。教材、フィールド、広報といった分野で、それぞれの強みや個性を活かし、立場を超えて力を発揮する。地域と協力して、教育をエンパワーメントする仕組みをつくることが、必要とされているのではないでしょうか。
 |
お話を伺った方 |