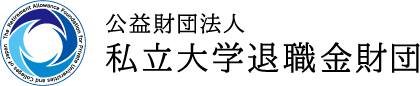豊橋創造大学 地域連携・広報センター
未来を拓く学校人Date: 2025.03.21
学生の自主性を高める!
「超・地域密着」で挑む連携事業

※2025年3月発行BILANC vol.36に掲載。インタビュイーの役職等は取材時のものです。
構成:布施 恵
撮影:川島英嗣
編集:プレジデント社
~産官と協働を推進。ブランディングを高める
豊橋創造大学を設置する藤ノ花学園 の歴史は1902(明治35)年開設の豊橋裁縫女学校に始まりました。地元(愛知県豊橋市)住民の要望を受け、公私協力方式の大学として、1983(昭和58)年に豊橋短期大学(現・豊橋創造大学短期大学部)、1996(平成8)年に豊橋創造大学を発足。次世代を担う創造性豊かな人材育成を目標に、「地域」「職業教育」「人間教育」を教育理念としています。
地域連携事業に力を注いでいる藤ノ花学園において自治体、産業界等との懸け橋になっているのが「地域連携・広報センター」です。以前は主に地域貢献や学校のPRを担当していましたが、社会環境の変化に対応するため、より特色を打ち出すことが重要だと考えました。そこで、これまで「貢献」の意味合いが強かった活動を「連携」とするため、ミッションやブランディングを徹底的に見直し組織を改編。2018(平成30)年に「地域連携・広報センター」として生まれ変わり、地域からの信頼獲得を目的に、豊橋市や新城市、国土交通省、豊川市民病院などの行政機関、サーラグループ、豊橋鉄道などの地元企業と連携を推進しました。そうして、大学のブランディングを強化し、入学者の増加や学生のさらなる学びにつなげています。
 |
豊橋創造大学 事務局長 吉原 郁仁さん 行政とつながり 市民にとって親しみある キャンパスをつくる |
~地域との一体化が大切。子育て支援の新しいカタチ
短期大学部の保育分野を活かした連 携事業の一つが「つどいの広場」です。
「『つどいの広場』 ![]() は現在豊橋市内に4か所ある、0~3歳の乳幼児と保護者を対象にした遊びや交流の場。豊橋市こども未来部との連携事業として2022年4月からその一つを大学内に開設しています。短期大学部幼児教育・保育科の学生との交流や教員によるミニ講座、大学図書館と協働した絵本の読み聞かせなどを行っています。学内には専門の先生も在籍しているので、子育て相談や講座は有意義なものになりますし、学生にとって実践になる。さらに多数の絵本や育児書を所蔵する大学図書館の活性化にもつながりました」
は現在豊橋市内に4か所ある、0~3歳の乳幼児と保護者を対象にした遊びや交流の場。豊橋市こども未来部との連携事業として2022年4月からその一つを大学内に開設しています。短期大学部幼児教育・保育科の学生との交流や教員によるミニ講座、大学図書館と協働した絵本の読み聞かせなどを行っています。学内には専門の先生も在籍しているので、子育て相談や講座は有意義なものになりますし、学生にとって実践になる。さらに多数の絵本や育児書を所蔵する大学図書館の活性化にもつながりました」
そう話すのは、「つどいの広場」を学内誘致に導いた事務局長の吉原郁仁さんです。
つどいの広場では、幼児教育ゼミの学生が月1~2回、「学生さんとあそぼう」というイベントを開催しています。実習での学びを実践として活かせる機会であると同時に、外部への実習と比較して自らが主体となって企画を遂行する場となっているそうです。
「地域に根差した大学を目指すならば、市民とのつながりは必要不可欠。気軽に構内へ出入りできる、地域と一体化した大学を目指しています。行政とつながれば、大学は市民とつながることができます。『つどいの広場』の誘致は、これを体現した良い例になったでしょう。学内を歩く親子連れの姿が、本学では今や日常の光景となりました。行政施設を構内に誘致した事例は他大学からの関心も高く、問い合わせも増加しています」

豊橋創造大学のつどいの広場の様子 ![]()
~未来を切り拓く知的・人的資源の活用
「2024年7月からは豊橋鉄道との新たな産学連携をスタート。その背景には、さまざまな要因による運転手不足に加え、2024年問題、労働人口の減少や利用客の減少など、同社が抱えていた“公共交通機関”ならではの諸問題がありました。また、本学にとっても同社は、通学のための路線バスを運行する会社として欠かせない存在。その維持・継続に協力できないかと考え、大学が持つ人的・知的資源の活用と、私たちが得意とする健康経営分野での支援など、地域社会との協働・発展を目的に連携に至ったのです」
そう振り返るのは、地域連携・広報センター長の平松靖一郎さんです。
 |
豊橋創造大学 地域連携・広報センター長 平松 靖一郎さん 人と人をつなぎ 学びを実用化に導く 懸け橋になることが役目 |
「2024年8月、連携協定を結んだ豊橋鉄道と最初の取り組みとして『豊橋観光スポットめぐり日帰りバスツアー』を開催しました。開催時期が学生募集と重なっていたこともあり、集客も視野に入れながら、地元の魅力をふんだんに詰め込んだツアーを企画。学生自らが学生目線で『豊橋』を自慢できる場を企画、ツアーガイドも務めてくれました」
豊橋鉄道の路面電車やバスに乗って市役所や豊橋医療センター、チョコレート菓子・ブラックサンダーの工場見学や渡し船・牛川の渡しの乗船体験、道の駅でキャベツや電照菊など特産品の紹介も行ったそうです。

「豊橋観光スポットめぐり 日帰りバスツアー」の様子 ![]()

公道として学生の通学の足でもある牛川の渡し。
加えて、2024年で100周年を迎えた豊橋鉄道の記念事業「豊鉄グループ感謝祭」では、豊橋創造大学の看護学科と理学療法学科によるワークショップ「高齢者疑似体験」を実施しました。
「来場者には高齢者疑似体験キットを装着してもらって、電車の乗り降りを試していただきました。お年寄りの大変さを知ることで、社会問題を考えるきっかけになったと思います。学生は豊橋鉄道のスタッフと関わる中で、運転手以外の職務を知ることができたでしょう。これをきっかけに、就職先として鉄道事業者にも関心を持ち、同社が抱える課題解決の一助になればいいですね」(平松さん)
豊鉄感謝祭ではこのほかにも、経営学科によるAIロボット体験・プログラミング、短期大学部のキャリアプランニング科が製作した豊橋のSDGsを考える地元すごろくなど、学科の特性を発揮したワークショップを実施しました。

豊鉄グループ感謝祭に親子で楽しめる体験ブースを出展したときの様子 ![]()
~活動で広がる視野・人脈。SDGsを見つめなおす
2022年からは、地域のインフラを担っているサーラコーポレーションとの連携をリスタート。「暮らし創造LABO」「学び共創LABO」の2つのプロジェクトでは、定期的に打ち合わせを行い、生活・学び関連の事業を進めています。その最初のプログラムが「カレーの衝撃」です。本イベントのファシリテーターを務めた豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科の准教授・瀧﨑優佳さんは、次のように説明します。
「『カレーの衝撃』は、誰もが知っている“カレー”を題材にグループワークをする中で、自身の価値観やキャリア、さらにはSDGsについて考える機会を提供するワークショップです。カレーという身近な食べ物から、SDGsの取り組みについて考えてもらうこのワークショップは今年で5回目を迎えました」
また2024年12月に行われたサーラグループとの共催企画「SDGs Do(ど)いいね!」では、「カレーの衝撃」の集大成イベントとして、出荷できないさつまいもや冬瓜などの野菜の活用方法を考えました。
「農家や食品業者から集めた規格外の食材でつくった、SDGsランチは来場者に大好評でした」(瀧﨑さん)
 |
豊橋創造大学 キャリアプランニング科 准教授 瀧﨑 優佳さん 身近なものに目を向け 自ら考え実践することが 問題解決の一歩に |
さらに、花の栽培・出荷が盛んな東三河はフラワーロスもSDGsの大きな課題。
そこで、瀧﨑ゼミがサーラグループと企画したのが「スマイルフラワー大作戦」です。第1弾は茎が少し曲がっているだけで、捨てられてしまう菊に着目。廃棄予定の菊を農家から提供してもらい、花弁をカラフルに染め上げる“カラーリングマム”体験を企画しました。第2弾は消費者の手に渡らず捨てられてしまう花材と、環境にやさしいバイオプラスチック製のタンブラーを使って、お正月飾りをつくるイベントを行いました。
第1弾の発案者である太田夢乃さん(豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科2年)は、サーラグループとの定期的な打ち合わせが、本プロジェクトの成功につながったと話します。
「売りに出せないものが、少しの工夫でみんなに行き渡る。その考え方に気付けたのは、日々サーラさんと話し合う場があったからだと思います」
このプロジェクトが自身にとって大きな学びになったと続けるのは、第2弾の発案者・竹田愛花さん(同)。
「身近な食材や植物の活用がSDGsにつながることを知り、自分にはない新しい考え方と課題解決のきっかけをいただきました」
また、プロジェクトの企画・立案に関わった山平美結さん(同)は、「農家の方の実体験を聞いて見えていなかったものに気が付き、人と人とのつながりを実感した」と振り返ります。学生の取り組みを見守ってきた瀧﨑さんは、「企業の考えをじかに触れられる場は、学生にとって非常によい刺激になっている。イベントに向け、自主的に考え、行動する姿に成長を感じました」と話します。


左:「「スマイルフラワー大作戦」第2弾」の様子 ![]() 。右側:プロジェクトの話し合いをする瀧﨑ゼミのみなさんの様子。
。右側:プロジェクトの話し合いをする瀧﨑ゼミのみなさんの様子。
~まずは継続すること。定期的な情報発信が要
今後は豊橋市のみならず東三河全域や、学生の約25%を占める静岡西部エリアでの連携活動を推進しつつも、より“地域に根差した大学”としての活動に力を入れていきたいと平松さんは強調します。
「人と人をつなぎ、大学のアカデミックな部分を実用化へ導く“懸け橋”になることが、地域連携・広報センターの役目。1000人規模の学生の顔が見える大学だからこそ、市民と関わりを持ち、大学が街にあることの意義について知っていただくことは非常に重要だと考えています。活動規模は小さいかもしれませんが、とにかく継続すること。そしてしっかり情報発信することが、地域に良い暮らしを提供し、地域に根付いた大学として存続するために大切ではないでしょうか」
※ 私立大学退職金財団では、教職員の皆様にスポットをあてた「未来を拓く学校人」の情報を募集しています。掲載をご希望の維持会員は、当財団までご連絡ください。