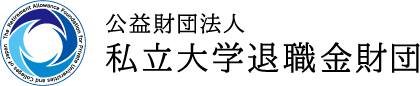相模女子大学 夢をかなえるセンター
未来を拓く学校人Date: 2024.07.22
地域と連携し、学生の夢を応援!
キャリア形成支援の新しいカタチ

※2024年7月発行BILANC vol.34に掲載。インタビュイーの役職、学年等は取材時のものです。
構成:秋山真由美
撮影:森本真哉
編集:プレジデント社
~多種多様なプロジェクトで強みとスキルを培う
地域連携に取り組む大学は数多くありますが、中でも日本経済新聞社が実施する「地域貢献度ランキング」で、2011年から9期連続の1位(女子大学部門)に輝いているのが、相模女子大学です。
相模女子大学には、地域連携を含めた正課外の活動、就職活動、生涯学習から、学生のキャリア形成支援を推進する「夢をかなえるセンター」があります。
「夢をかなえるセンター」の多岐にわたる取り組みの中で、特筆すべきが「Sagamiチャレンジプログラム」です。これは、週末や長期休暇を利用して、全国の地域で3日~1週間程度を過ごす正課外プログラム。企業と連携した商品開発や、海外に子ども用車椅子を届ける活動、被災地復興支援活動など、国内外で多種多様な取り組みを行っています。学生にとっては、実際に地域に入り込むことで社会課題を学ぶきっかけになり、地域にとっても、学生の専門性や活力をまちづくりに生かすことができるため、双方にメリットがある事業です。
活動形態は、ボランティア、体験活動、地域協働活動、プロジェクト活動、国際教育活動に分類され、プロジェクト活動は1年間の参加が基本。一部の活動を除き単位には認められていませんが、学生が現地での体験から自分の強みやスキルを培い、キャリア形成について気づきを得るための機会が連続的に設けられています。コロナ禍で一時的に減少してしまったそうですが、2024年1月時点で、全学生の23%の学生が参加しています。
~PDCAサイクルを回し自己分析と成長を促す
「2008年から、社会マネジメント学科の学生向けに始めた、鳥取県境港市との連携プログラムが始まりです。それと同時期に、農林水産省が主催する〝田舎で働き隊!″に、女子大学としては全国で初めて、本学の学生が参加しました。福島県本宮市、三重県熊野市などの自治体と連携し、そのご縁から学生が現地を訪問するだけではなく、現地の方々と一緒に、相生祭(学園祭)で各地域の特産品を販売するようになり、連携の輪が広がっていきました」
そう解説するのは、人間社会学部 社会マネジメント学科教授の湧口清隆さんです。
最初は学科としての取り組みでしたが、学科外からも地域活動への参加を希望する学生が増えたことで、大学を挙げて取り組むべき活動だと、職員間で認知されるようになったそうです。
しかし、全学的活動に移行した当初、これらの正課外活動は単位を取得できないばかりか、目的や意義が明確でなく、学生も何のために参加しているのか自覚できないままになっていました。そこで、専用のシラバスを作成し、プログラムの概要と併せて各地域が抱える課題や活動目標を提示。学生が、活動に参加する上での目標を設定し、終了後には振り返りを行って、気づきや課題を次の活動に生かすPDCAサイクルで、継続的な学びにつなげられる仕組みを構築していきました。
「これを『マーガレットスタディ』(マーガレットは学花)と呼んで推進しています。参加している地域のために何が有効なのか、学生自身が試行錯誤し、実体験を通してPDCAを回すことで、正課授業では見つけられなかった自分の強みやスキルを発見し、キャリアについても新しい視点から考えられるようになっていきました」(湧口さん)
 |
相模女子大学 専門職大学院 社会起業研究科 人間社会学部 社会マネジメント学科 教授博士(商学) 湧口 清隆さん 地域連携の継続には 学生と地域社会の Win-Winの関係性が大事 |
~活動を通じて広がる視野・興味・人脈
現在、Sagamiチャレンジプログラムでは、農業体験や特産品の販売、伝統芸能の体験など、30以上のプロジェクト活動を用意しています。
中でも人気の活動が、三重県熊野市にある棚田・丸山千枚田の保存活動に参画する「丸山千枚田魅力発信プロジェクト」です。リーダーの横井碧さん(人間社会学部 社会マネジメント学科2年)は、1年生の時にSagamiチャレンジプログラムについて知り、まず2泊3日の田植え体験に参加したと振り返ります。
「きっかけは、三重県に行ってみたいという単純な動機でした。でも、実際に田植えを手伝ってみると予想以上に大変な作業でした。受け身でいては何をして良いかもわからず、地域の方々や先輩方の足を引っ張っていると感じたこともありました。それでも地域の皆さんが温かく、孫のように可愛がってくれ、途中から自ら進んで行動出来るようになりました。」
 |
相模女子大学科 人間社会学部 社会マネジメント学科2年 横井 碧さん いまや熊野が第二の故郷 活動で価値観が変わり 将来の方向性に変化 |
「その後も何度か訪問して交流を続けるうちに、熊野市やそこに住む皆さんへの想いも増し、今では第二の故郷のように思っています。入学当初は、自分のやりたいことが明確ではありませんでしたが、この活動をきっかけに価値観や考え方が変わり、地域づくりや福祉に興味をもつようになりました。今では千枚田のオーナー数の伸び悩みなどさまざまな課題を解決したいと考えています」

横井さんが参加した、「丸山千枚田魅力発信プロジェクト」活動の様子。昔ながらの手作業での農業体験を行う。
「Sagamiチャレンジプログラムに参加した学生は、自身のキャリアプランが明確になり、積極的に就職活動を進められる傾向がある」と話すのは、夢をかなえるセンター 連携教育推進課 社会連携推進室 係長の三木若葉さんです。
「プロジェクト活動に参加したことによって、コミュニケーションスキルやプレゼンスキルが向上した学生は非常に多いです。活動で得た経験や知識を生かして就職先を選ぶ学生も増え、公務員や農協など、これまで想定されてこなかった進路を目指す学生も増えました。
子ども教育学科で小学校教諭を目指して学んでいた学生が、新潟県佐渡市のプロジェクト活動に参加したことで、地域のためになる仕事をしたいと進路を変更し、地元の信用金庫に就職した例もあります。また卒業後、アドバイザーとして後輩の支援に携わる卒業生も増えています」(三木さん)
 |
相模女子大学 夢をかなえるセンター 連携教育推進課 社会連携推進室 係長 三木 若葉さん 社会との関わりの中で 自分の軸を見つけ 人生を切り拓いてほしい |
~双方にメリットがある関係の構築が大切
夢をかなえるセンターでは、学生を各地域に送り出して終わるのではなく、その後も学生と地域との交流が継続できるような工夫をしています。地域連携を継続していくには、学生にとっても、地域にとっても、Win-Winの関係を構築することが大事だと湧口さんは言います。
「例えば、相生祭で開催している地域物産展では、地元・相模原市はもちろん、学生たちが活動を行う全国各地の生産者団体にも参加いただき各地域の名産品を販売しています。日頃学生たちがお世話になっている各地域と本学が立地している相模原市の方々を結ぶ催しであり、毎年約2万人が来場する相生祭の目玉企画の一つです。地方の生産者さんにとっては、学園祭に出店すれば、直接消費者の声を聞くことができ、自分たちの商品を首都圏に広げていくためのヒントが得られるのです」
地域物産展の盛況ぶりが話題になり、小田急百貨店(町田店)で地域連携フェアとして相模女子大学と連携・交流のある地域や企業の商品を販売するイベントを過去数年間にわたり開催したことも。「学生にとっては、地域の商品を自分が体験したストーリーとともにお客様にアピール・プレゼンするいい機会になります。この経験によって進路を鉄道会社のグループ企業に決め、バイヤーとして地域と関わった卒業生もいます」(湧口さん)
~近隣地域との連携を強化。未来を担う女性の育成へ
各地域との連携に力を入れてきた相模女子大学ですが、今後は近隣地域との連携を強化したいと意気込みます。
「これまでは神奈川県外地域との連携が多く、評価されてきました。今後は、蓄積してきた知見を地元のまちづくりにも還元したいです。過疎や地域振興への知見は神奈川県にも役立つはずです。2024年度からは、神奈川県内の高校の探究学習支援を担当しますので、本学併設校の高等部だけではなく、地元の高校生でも、横浜発祥のベーカリー『ポンパドウル』のレシピ開発や、本学キャンパス内にある梅の実収穫(収穫後、地元酒造とともにオリジナル梅酒をつくる)などに参加いただけるよう、活動を広げたいと考えています」(三木さん)

相模原女子大学の構内には約100本もの梅の木が実をつける。
多様な価値観をもつ学生たちのキャリア形成を考え、さまざまな選択肢の用意が求められる昨今、夢をかなえるセンターの取り組みは学生と社会がより良くつながる手掛かりになるかもしれません。
「そもそも、学生生活は正課の学びだけで送るものではなく、サークル活動もあれば、アルバイトもある。その中に、正課外の活動もあっていいはずです。社会との関わりを積極的に増やしながら、自分の道を見つけてもらいたいと思っています。いろいろなことに挑戦しながら、主体性や柔軟なコミュニケーションスキルを育み視野を広げ、自らの人生を切り拓いていってほしい。その機会を提供するのが、私たちの使命です」(三木さん)
「〝見つめる人になる。見つける人になる。〟という本校のスローガン通り、課題発見力と発想力に富んだ女性を育成していきたいと思っています。不確実性が高い時代において、どんな場所でも、明るい社会を築いていけるような賢く温かい女性、柔軟なコミュニケーションでさまざまな人と協働できる人になってほしい。Sagamiチャレンジプログラムを通じて、社会課題に目を向け、豊かな発想の源泉になる体験を積んでもらい、リーダーにもサポーターにもなれるような人材を育成することで、大学としての使命も果たしていきたいです」(湧口さん)
※ 私立大学退職金財団では、教職員の皆様にスポットをあてた「未来を拓く学校人」の情報を募集しています。掲載をご希望の維持会員は、当財団までご連絡ください。